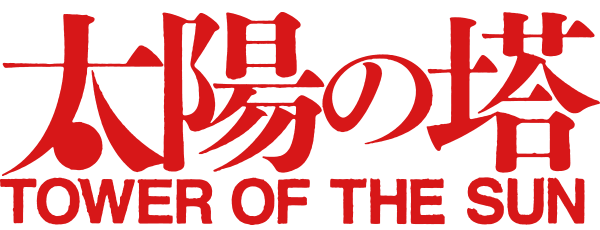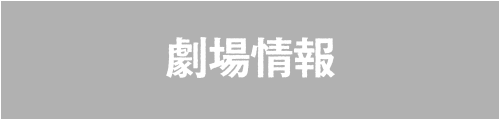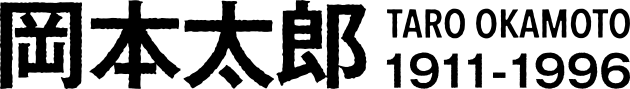
1911年生まれ。岡本一平とかの子の長男。東京美術学校に入学、父母の渡欧に同行し、1930年からパリに住む。数々の芸術運動に参加しつつ、パリ大で哲学・社会学・民族学を専攻、ジョルジュ・バタイユらと親交を深める。帰国し兵役・復員後、創作活動を再開、現代芸術の旗手として次々と話題作を発表した。1970年の大阪万博テーマ館もプロデュース。一方、旺盛な文筆活動も続けた。1996年没。

- 1911年
- 漫画家の父・一平、歌人の母・かの子の長男として生まれる。
- 1929年
- 東京美術学校(現・東京藝術大学)に入学。両親とともに神戸港を出港。
- 1930年
- パリに到着。パリでの生活をはじめる。
- 1933年
- アプストラクシオン・クレアシオン(抽象・創造)協会に最年少で迎えられる。
- 1936年
- サロン・デ・シュランデパンダン展に《痛ましき腕》を出品。
- 1937年
- パリ万博跡地にミュゼ・ド・ロム(人間博物館)が開館。
パリ大学民族学科の学生として同館でマルセル・モース教授に民族学を学ぶ。
- 1940年
- 帰国し、42年より戦争へ出兵。
- 1946年
- 復員するも戦災で作品もろとも自宅は焼失。
- 1948年
- 花田清輝らと「夜の会」を結成。前衛芸術運動をはじめる。独自の芸術理念「対極主義」を提唱。
- 1949年
- 第34回二科展に《重工業》を出品。
- 1950年
- 第35回二科展に《森の掟》を出品。
- 1951年
- 東京国立博物館で縄文土器を見て衝撃を受ける。
- 1952年
- 「四次元との対話―縄文土器論」を発表。
- 1954年
- 坂倉準三設計のアトリエ(現岡本太郎記念館)が青山に完成。「現代芸術研究所」と名づけ、新たな芸術運動の拠点に。『今日の芸術』を刊行。
- 1956年
- 丹下健三設計の旧東京都庁舎に7面の陶板レリーフ壁画を制作。縄文土器論を収録した『日本の伝統』を刊行。
- 1957年
- 日本各地を精力的に取材した「芸術風土記」を『藝術新潮』に連載。
- 1959年
- 沖縄を訪れ、御嶽(うたき)に感動する。
- 1961年
- 『沖縄文化論』を刊行。
- 1964年
- 丹下健三設計の国立代々木競技場に8面の陶板レリーフ壁画を制作。
- 1967年
- 大阪万博のテーマプロデューサーに就任。《明日の神話》の制作を開始。
- 1969年
- メキシコにて《明日の神話》完成。
- 1970年
- 大阪万博*開幕。シンボルゾーン中央に太陽の塔を含むテーマ館が完成。
- 1975年
- 太陽の塔の永久保存が決定。
- 1993年
- 太陽の塔の大規模改修工事完了。
- 1996年
- 逝去。
- 1997年
- 財団法人岡本太郎記念現代芸術振興財団設立。
- 1998年
- 岡本太郎記念館開館。
- 1999年
- 川崎市岡本太郎美術館開館。
- 2006年
- 《明日の神話》の修復完了。東京・汐留にて初公開。
- 2008年
- 東京・渋谷駅の連絡通路に《明日の神話》が恒久設置される。
- 2011年
- 生誕100年事業「TARO100祭」が開催される。
- 2018年
- 太陽の塔の耐震補強/内部再生工事が完了し、恒久展示施設としてオープン。半世紀ぶりに内部の一般公開がはじまる。
*大阪万博・・・正式名称は、日本万国博覧会。大阪府吹田市の千里丘陵にて、1970年3〜9月までの約半年間開催。アジア、日本初の国際博覧会として、「人類の進歩と調和」をテーマに、77カ国が参加し、約6.400万人を動員。2010年の上海万博まで、世界最多の動員数を誇った。会場施設の設計を統括する基幹施設プロデューサーを丹下健三が、テーマ展示の制作を担うテーマプロデューサーを岡本太郎が務めた。